| 1)火山と温泉 |
ても、いろいろな鉱物成分などを含んでいれば、温泉という名称で呼ばれる
事になる。しかも、近頃では技術の発達により、自然に湧き出るものだけ
とはかぎらなくなってきた。
ボーリングにより地下の温泉を掘り、ポンプで汲み上げる方法が取られる
ようになり、ますます温泉の数は増えている。
日本は火山国であり、日本列島には北から南まで火山が分布している。
現在、地球上でもっとも火山活動が盛んな所は、太平洋をとりまいている
環太平洋火山帯であるが、この中に日本も含まれているのである。
一般に火山と呼ばれる山は、もっとも新しい地質時代の第四紀(約200年
前から現在まで)に噴出したもので、その中には現在も活動を続けている
活火山も含まれている。
火山の噴火は地下から熱い溶岩や水蒸気が噴出する現象であり、温泉は
地下から暖かい水が湧き出てくる現象である。
火山地帯には温泉が多いことなどから考えると、温泉は火山活動と密接な
関係を持つことが解かる。しかし、中には福島県東南部、兵庫県南部、四国
など、第四紀火山のないところにも25度以上の温泉が湧出している事が
ある。しかし、これも第四紀より古い第三紀の火山活動と重なる。
又,四国の道後温泉は、もっと古い白亜紀の火山活動が熱源となっていると
言われている。
地下の大きな熱源は、人間の歴史のスケールでは計り知れないほどのサイ
クルで熱を発散させ続けているのである。
-------------------------
***ちょっと一服の資料***
 (拡大)・・・大きいです。
(拡大)・・・大きいです。・旅館が1泊2食で1円50銭という時代に作られた色つきのリーフレット
表紙がそのまま、葉書としても利用できるというアイデアの豊かさに
頭が下がる。製作は役場が担当。
top
| 2)温泉の誕生 |
複雑な要素がその誕生に関わるために、その誕生も様々で多くの未解決
の事項が残されている。
温泉の成因についての科学的研究が行われるようになったのは、十九
世紀の半ば頃であり、そこには、水はどこからくるのか、熱源は何なのか
温泉に含まれている成分はどこからくるのか、何故自然に湧き出すのか
など、沢山の問題が含まれている。
温泉の水については、大きく分けて、循環水説とマグマ水説とがあるが、
循環水説を初めて世に送り出したのは、ドイツのブンゼンである。ブンゼン
は、アイスランドの温泉を研究し、1847年に天水(雨水など)が地中に入っ
て地下水となり、火山等の地下の熱に暖められ、岩石中の様々な成分を
溶解してふたたび地表に温泉として湧出するという説を打ち立てた。
同じく1847年、フランスのドボーモンは、火山発散物と温泉の含有成分が
似ている事から、温泉の成分はマグマからにじみ出た物だという説を出
した。その後、1902年にオーストラリアのジュースが、カールスバード温泉
(オーストリア)の湧出量がこの地域の雨量に比較して多い事や温泉水中
の二酸化炭素、ナトリウム、塩素などの成分が湧出母岩の花崗岩中には
非常に少ないことなどから、水も含有成分も地下深部にあるマグマから
上昇してきたマグマ水だという説を出した。
この温泉水が、地中からはじめて地表に出る水であることから『処女水』
という魅力的な言葉を作り出した。
温泉水の起源については、その他にも海水説や、マグマが冷却する時に
分かれた熱水溶液だとする説など、様々な説が出されたが、今日では
様々な観測や分析のデータを検討した結果、マグマ水や化石海水、ある
いは現在の海水等も混入することはあるが、少なくとも大多数の温泉は
循環水が主体であることが知られている。
温泉の誕生については、この循環水が温泉水の主な起源であると考え
ると、おおざっぱに次のように考えることが出来る。
地上に降った雨水の一部はすぐに蒸発するが、大部分は流水となって
地中にしみ込み地下水となる。地球内部は、地下深くなればなるほど
しだいに温度が上がってくる。又,火山地帯では、地下数キロから十数
キロという比較的浅いところに地球内部から上昇してきたマグマが、
マグマ溜まりを作り、千度以上の高温度に保たれて熱を発散し、地表
に溶岩やガスを噴出して火山活動を行っているところがある。
マグマ溜りは、通常数万年の寿命を持ち、ある程度冷却し、結晶化
して岩石となった後も、高温岩体として長く熱を出し続ける。温泉は、
地下に入った地下水が、この地下の熱源により暖められ、時には
マグマのガス成分やマグマから分かれた熱水溶液が混入し、まわりの
岩石の成分も溶解して、温泉水をなり地上に湧出すると考えることが
できる。
***ちょっと一服の資料***
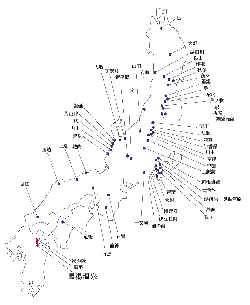 (拡大)(リンク版)
(拡大)(リンク版)・体に効く温泉地・・・医学博士「植田理彦先生」の著書
「からだに効く温泉宿」に記されている日本の温泉地マップ
(リンク版・・・各温泉地のmapリンク)
-----------------------------------------------
top
| 3)温泉の定義 |
温度が25度以上あるか、25度に達していなくても、温泉成分のどれか
一つが規定量以上含まれていれば、温泉と定義されることになっている。
この温泉法では、液体でなくても、地下から出る水蒸気その他のガス
(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)も、温度あるいは成分が条件を
満たしていれば温泉とされることになっている。
温泉法が制定されたのは、温泉の開発に伴って、湧出量の減退、温泉
の権利に関する紛争などの問題が出てきて、温泉の保護と適正な利用を
図るために、法律をつくる必要が生じたからである。
有効成分が含まれていれば、たとえ水であっても加熱して入浴、療養に
利用することが出来るし、水蒸気なども温泉として利用することが出来る。
top
| 4)温泉の分類方法 |
分類法には、泉質だけでなく、温度・水素イオン濃度・浸透圧・湧出形態
など、いろいろな分類法がある。
温泉の温度で分ける分類法では、温泉の湧出口の温度によって、25度
未満の冷鉱泉、25度〜34度までの低温泉、34度〜42度までの温泉、
42度以上の高温泉に分けることが出来る。
水素イオン濃度(pH)による分類法では、
pH3未満 の酸性泉
pH3〜6 の弱酸性泉
pH6〜7.5 の中性泉
pH7.5〜8.5 の弱アルカリ泉
pH8.5以上 のアルカリ性泉 に分類される。
酸性泉は、物を溶かす力が強いため、温泉水中に含まれる含有成分が
多くなり、アルカリ性泉は反対に物質が沈殿ンしやすいため、含有成分
少ない水質になりやすくなる。
溶けている成分の濃度によって違う、温泉水の人体に対する浸透圧で
分類方法では、人体の細胞の浸透圧より低浸透圧を持つ『低張泉』
溶存物質グラムが8グラム未満、ほぼ等しい浸透圧を持つ「等張泉」
(8〜10グラム)、それ以上の浸透圧の「高張泉」(10グラム以上)に
分けられる。
高張泉では、温泉の成分が細胞膜を通して人の体内にもっとも入り
やすいことが、データによって確認されている。
浸透圧による分け方と似ている分類法に、人体に対する作用の刺激の
強さによる分類法もある。
刺激作用の強い物を「緊張性」といい、泉質による分類では、酸性泉、
単純炭酸泉、硫黄泉炭酸鉄泉、緑礬泉がこれに含まれる。
刺激の弱い物は「緩和性」といい、単純泉、食塩泉、重曹泉、芒硝泉、
石膏泉、重炭酸土類泉、放射能泉が含まれる。
top
| 5)泉質による分類 |
の種類やその割合等の化学組成に基づき、温泉を医学的な治療に利用す
る療養泉としての要素を大きく考慮して行われる。
温泉水の中には非常に多くの物質が溶け込んでおり、その大部分はプラ
スかマイナスの電気を帯び、陽イオンか陰イオンとなって存在している。
このような温泉水を蒸発乾固させると、溶存成分の陽イオンを陰イオンが
結合して、炭酸水素塩(重炭酸塩)、塩化物、硫酸塩などの形の塩類と
なって析出する。
主な塩類の他に、硫黄、硫化水素を始め、水質の酸性に寄与する水素
イオン、少量ないし微量含まれる銅、臭素、ラドン、ラジウムなどの成分や
ガス成分の遊離二酸化炭素(炭酸ガス)など医学的に有効な成分が分類
の考慮に入れられる。
さらに、溶存固形成分が少量(温泉水1キログラム中に1グラム未満)で、
泉温が25度以上の物も分類上一つの泉質され、合計11種の泉質に大別
されている。
***ちょっと一服の資料***
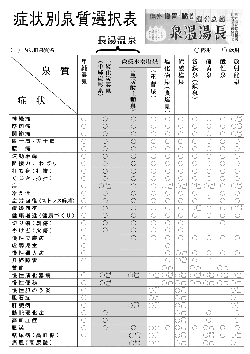
・・・症状別泉質選択表・・・
これで、10種の泉質がわかります。
(拡大)
******
11種の泉質のうち、日本にもっとも多いのは単純泉と食塩泉、ついで
重曹泉、硫黄泉、硫酸塩泉が見られる。
温泉は天然水であるから、多くの成分がいろいろな割合で含まれている。
したがって、無数にある温泉のそれぞれの化学素性はすべて異なって
いる。これらの温泉を分類するには、11種の分け方ではどこにもいれられ
ないという温泉がでてくる。
そこで、これらをもっと細かく分けていくことが必要となる。主成分や含成分
を組み合わせて細かく分類する方法によって、泉質をもっと詳しくあらわす
方法もある。
この方法で分類すると、泉質は80種に分けられる。この分類方法では、
主成分と副成分の組み合わせによって分類するため、泉質名をみれば
その温泉がどんな温泉であるかが大体わかるようになっている。
含○○×泉という言い方をしている場合、主成分は×泉であり、副成分
として○○を含んでいることを意味している。
例えば、含炭酸重曹泉は、主成分は重曹で、炭酸を副成分として含んで
いることになる。単純温泉は、含固形成分が少ないものであり、純○○泉
は、純粋な○○を成分として含み、他の成分はあまり含まれていないと
いう意味である。
top
| 6)癒しとしての温泉 |
入浴に使われて来たが、古代の文献に温泉の記述が多く見られること
から考えても、温泉は古代から神秘的な自然の恵みとして、多くの人に
知られていたことがわかる。
湯浴みは心身を清める沐浴としての意味があり、『湯垢離(ゆごり)』と
呼ばれていた。
昔の温泉行きは湯治を意味していた。医学が発達する前の湯治は、貴重
な医療法であり、人々は温泉の持つふしぎな力に恐れと尊敬とをもって接
していた。しかし、今の温泉はおもに行楽地であり、医学の発達した時代
の温泉療法は、迷信と紙一重の世界だと思われている。
しかし、温泉療法の効果は、科学的にも証明され、自然の持つ治癒力に
再び人々の目が集まってきた。温泉療法は、何故、体に効果があるのだ
ろうか。どんな病気に効くのだろうか。おおまかに見てみよう。
温泉療法の効果は、最近の温泉医学の見解によれば、温泉水の含有
成分による化学的薬理作用と温泉水の熱、水圧、浮力などの物理的作用
に加えて、温泉地の自然環境や転地効果など、いろいろな要素が総合的
に働いてもたらされると考えられる。
物理的作用による温度効果は、泉温と皮膚温との温度差が大きい程
大きくなる。熱い湯や冷たい湯に入ると、皮膚の血管は緊張して収縮し
(血圧上昇)、やがて熱い湯では拡張していく。
ぬるめの湯では、このような変動は少ないので、身体への影響は小さく
長時間の入浴が可能で鎮静効果が得られる。したがって、高齢者や体が
弱っている病人には、ぬるめの湯がすすめられる。
ぬるめの湯に長くつかると筋肉の凝りや関節の痛みも和らぐ。
水の浮力は体重を軽くするので、弱った筋力でも手足の運動が容易に
なる。また、温熱作用によって、筋肉の働きが良くなり、血流も増加して、
筋肉や関節の病気の回復(リハビリテーション)に大きな効果がある。
温泉中に含まれているさまざまな化学物質は、大部分がイオンの形で
溶け込んでいて、入浴によって一部が皮膚を通して体内に入る。
その量は治療薬を飲む場合に比べると極く少量であるが、全身の皮膚
からはいるので、全身的な薬理効果をひきおこす。吸収された温泉成分は
血液中に入り、細胞の働きに変化を与え、神経的にも影響を及ぼす。
したがって、この効果は泉質によって微妙に変化する。
泉温などによる物理的作用と含有成分による化学作用は、あいまって
身体全体の調子を変える変調変調効果となって現われ、一般に身体の
機能を高め、不調な時には正常にするといわれる。
しかし、病気などのために身体が弱っているときには、新陳代謝が進み、
体力を消耗して悪化させることもあるので、注意が必要である。
これらを総合した温泉療法は、薬物療法や外科治療のように、病気や
病原菌に直接働くものでなく、病人の身体に働きかけて、機能を正常に
戻し,運動や食事療法なども組み合わせて、病気に対する抵抗力や回復
力を高めることによって治療効果を現す。
***ちょっと一服の資料***
長湯で試みられた温泉治療(糖尿病)の講習会

(拡大)懐かしい姿があるのでは??
******
したがって、短時日で効果が上がるものではなく、ある程度の期間
(少なくとも1週間、普通は2〜4週間)が必要である。しかし、この期間を
過ぎると、温水に対する慣れがでて来て、効果が次第に低下してくるので
しばらくの間休みをはさんで治療を繰り返すのが良いとされている。
----------
【温泉徹底分析】おわり...
top